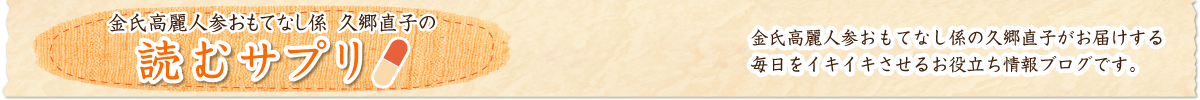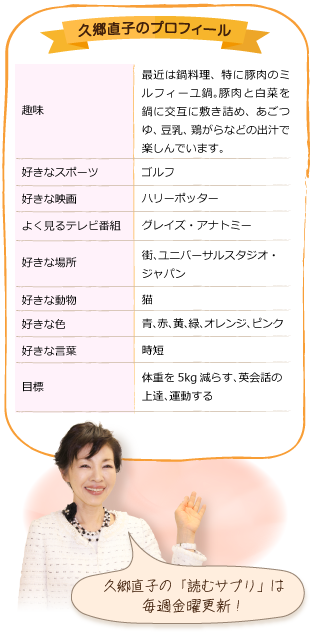日ごと気温が高くなり、そろそろ衣替えが必要な時期になりました。
弊社では一足早く、5月25日からクールビズ期間がスタートし、
男性社員はノーネクタイで過ごしています。
衣替えは、もともと中国の宮廷で行われていた習慣の1つ。
日本では平安時代に伝わり、室町時代から江戸時代にかけて定着したといわれています。
特に、江戸時代になると「この期間には、この服を着る」というように、
どの時期に何を着るのかが細かく決められていました。
その考えは根強く残り、
着物においては現代でも10月から5月は袷(あわせ)、
6、9月は単衣(ひとえ)、
7、8月は薄物(うすもの)を着ることが決められています。
また着物の場合、柄も考慮しなくてはなりません。
冬は、雪輪や枯山水、椿、南天、梅。
春は、芽吹きや蝶、桜。
夏は、藤やあやめ、魚や流水模様。
秋は、菊や萩、もみじ、月…など、
季節にふさわしい柄があり、それに合わせることが大切です。
ちなみに、着物の柄は実際の季節より早めの柄を身に着けるのが粋とされており、
例えば、桜が満開の頃に桜柄を着る野暮だといわれています。
四季がなければ衣替えなどせず、1年中似た服装で過ごせるのですが、
四季がある日本では季節に合わせて服装を変えることが必要です。
様々な種類の衣服が必要な分、収納スペースを確保しなければなりませんが、
その反面、衣服からも季節の移ろいを楽しめるという利点があります。
これから来る夏に思いを馳せつつ、徐々に衣替えを進めているこのごろです。
久郷直子