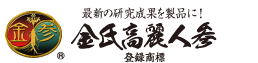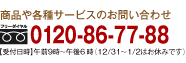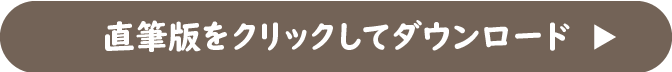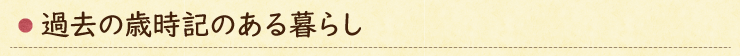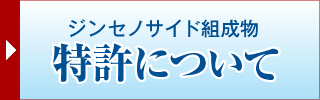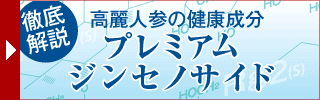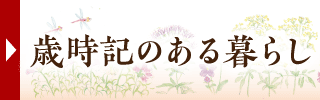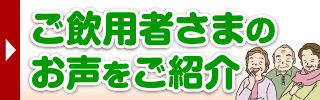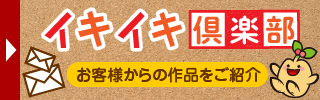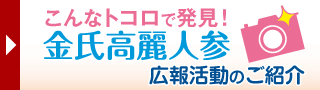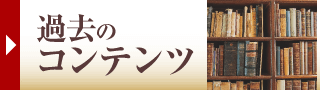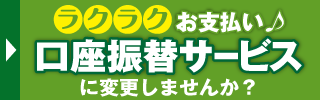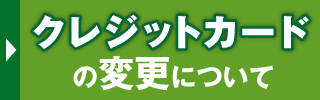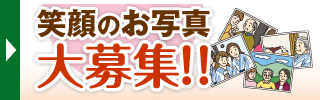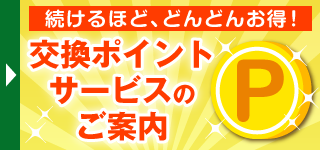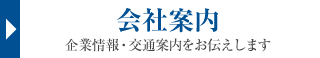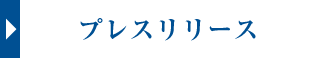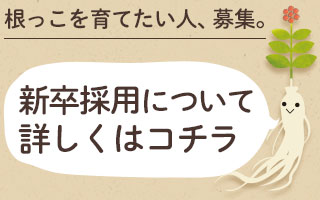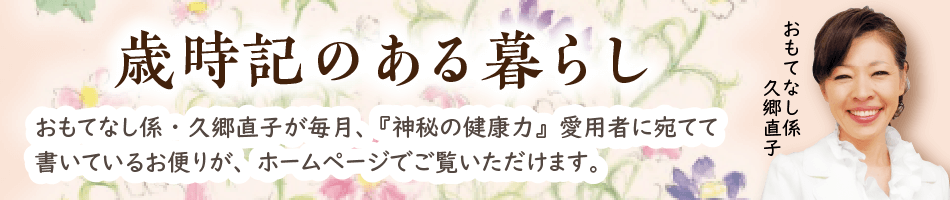
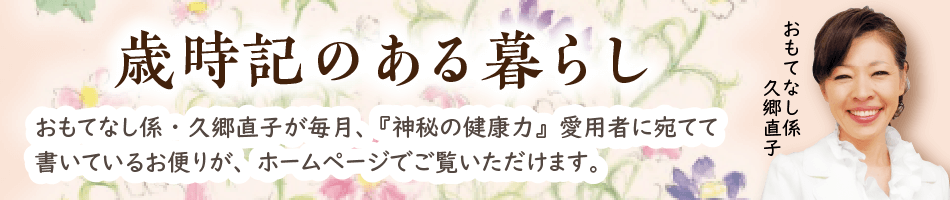
2026年2月 歳時記のある暮らし
寒さ厳しき折ですが梅の便りが届くころとなりました。
皆様、健やかにお過ごしでしょうか。
いつも『神秘の健康力』をご愛用いただき誠にありがとうございます。
二月、暦の上では「立春」を迎えますが、朝の霜や吐く息の白さに厳しい寒さを感じながらも、日差しには少しずつ春の柔らかさが宿ります。
七十二候では、初候「東風解凍(はるかぜこおりをとく)」、次候は「黄鶯睍睆(うぐいすなく)」、末候「魚上氷(うおこおりをいずる)」と、凍てつく日々の中にも川面の氷が溶け、鶯が初鳴きし、氷下の魚が動き出すという自然のようすから小さな春の兆しが見えてきます。
三日の節分は、冬と春の境目を表す大切な日で、旧暦の立春を境に「季節を分ける日」とされてきました。この日に豆まきや柊鰯(ひいらぎいわし)で鬼を追い払い福を招き一年の安泰を願います。
十四日のバレンタインデーは、洋の東西を問わず親しまれる行事です。日本ではチョコレートを贈る日として広まりましたが、その本質は感謝や思いやりを伝える機会にあります。大切な人へ贈る小さな甘さは寒い季節に心をほっと温めてくれそうで、春の兆しが楽しみな二月にふさわしいイベントです。
梅の便りが届くころです。梅といえば、菅原道真公にまつわる「飛梅伝説」が有名です。道真公は平安京朝廷内での藤原時平との政争に敗れ、延喜元年(九〇一年)に太宰府へ左遷されることとなりました。屋敷を離れることになり日ごろから愛でてきた梅や桜、松などの庭木との別れを惜しみ、梅の木に語りかけるようにこの歌を詠まれました。
東風吹かばにほひおこせよ梅の花 あるじなしとて春な忘れそ
この歌に呼応して、主のもとに都から太宰府へと一夜のうちに飛んできたと伝えられるのが、現在も太宰府天満宮の本殿右側にある御神木「飛梅」といわれます。ほかに桜や松もありましたが、桜は主人との別離の悲しみのあまり枯れてしまいます。松は梅と同様に道真公を目指して飛び立ちましたが太宰府までは届かず、全国各地に根を下ろして「飛松伝説」として名を残しています。こうして梅の木は、力強く凛とした姿で生きることの象徴となりました。
梅一輪一輪ほどの暖かさ
服部嵐雪の作品です。「一輪咲いている梅の花を見ると一輪ほどのかすかな暖かさが感じられる」とも「一輪咲くごとに、少しずつ暖かくなっている」とも受け取れます。
名残雪の野道を歩けば、フクジュソウの黄金色の輝きや、フキノトウの萌黄色を目にすることもあり、春の兆しを見つける喜びが感じられます。
凍てつく大地にまるで太陽のかけらを落としたかのように顔をのぞかせるフクジュソウは、名前も「福寿草」と書き、幸福や長寿を願う縁起の花として古くから愛されてきました。しかし、この美しい花の根や茎、葉には強い毒が含まれており、誤って口にすると命に関わることさえあります。山菜と間違えて採ってしまう事故も毎年のように報告されており、十分な注意が必要です。
一方、同じく早春の野に顔を出すフキノトウは、山菜の代表格。ほろ苦い味わいは冬の身体を目覚めさせる妙薬のようです。天ぷらやみそ和えにすれば、ほのかな香りと苦みが口いっぱいに広がり、寒さで縮こまった心身をほぐしてくれます。
同じ「春のしるし」でありながら、一方は観賞して楽しみ、もう一方は食卓で味わう。自然の中には、命を養う恵みと、慎重に距離を置くべき美しさが隣り合わせに息づいています。寒さの中に芽吹く力を感じながら元気に冬を乗り越えましょう。
健康対策には高麗人参 健康食品『神秘の健康力』。
皆様のご健康をお祈り申しあげます。
金氏高麗人参株式会社
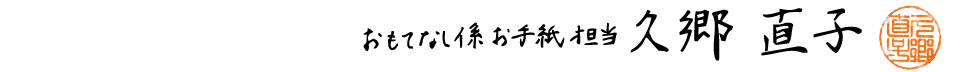
- 2026年1月の歳時記のある暮らし
- 2025年12月の歳時記のある暮らし
- 2025年11月の歳時記のある暮らし
- 2025年10月の歳時記のある暮らし
- 2025年9月の歳時記のある暮らし
- 2025年8月の歳時記のある暮らし
- 2025年7月の歳時記のある暮らし
- 2025年6月の歳時記のある暮らし
- 2025年5月の歳時記のある暮らし
- 2025年4月の歳時記のある暮らし
- 2025年3月の歳時記のある暮らし
- 2025年2月の歳時記のある暮らし
- 2025年1月の歳時記のある暮らし
- 2024年12月の歳時記のある暮らし
- 2024年11月の歳時記のある暮らし
- 2024年10月の歳時記のある暮らし
- 2024年9月の歳時記のある暮らし
- 2024年8月の歳時記のある暮らし
- 2024年7月の歳時記のある暮らし
- 2024年6月の歳時記のある暮らし
- 2024年5月の歳時記のある暮らし
- 2024年4月の歳時記のある暮らし
- 2024年3月の歳時記のある暮らし
- 2024年2月の歳時記のある暮らし
- 2024年1月の歳時記のある暮らし
- 2023年12月の歳時記のある暮らし
- 2023年11月の歳時記のある暮らし
- 2023年10月の歳時記のある暮らし
- 2023年9月の歳時記のある暮らし
- 2023年8月の歳時記のある暮らし
- 2023年7月の歳時記のある暮らし
- 2023年6月の歳時記のある暮らし
- 2023年5月の歳時記のある暮らし
- 2023年4月の歳時記のある暮らし
- 2023年3月の歳時記のある暮らし
- 2023年2月の歳時記のある暮らし
- 2023年1月の歳時記のある暮らし