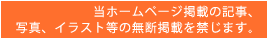最近、若い世代の間でも、漢方や東洋医学の人気が高まっています。即効性が期待できるものではありませんが、日々続けることで体調がよくなってくるなど、穏やかで自然な作用が理由の1つです。薬の副作用による悪影響を避け、時間をかけても安心して改善するまで続けることを選択する人が増えたということも言えるでしょう。
最近、若い世代の間でも、漢方や東洋医学の人気が高まっています。即効性が期待できるものではありませんが、日々続けることで体調がよくなってくるなど、穏やかで自然な作用が理由の1つです。薬の副作用による悪影響を避け、時間をかけても安心して改善するまで続けることを選択する人が増えたということも言えるでしょう。
私たちの体は、身体機能のバランスを保ち、常に健康でいようとする働きがあります。東洋医学では「未病」という言葉がありますが、これは病気とまでは言えないけれど、病気に向かいつつある状態のことです。例えば、手足の冷えや体のだるさ、胃腸の不調などです。未病の改善には、血流を改善し、体の総合的な力を高めることが大切なのです。健康診断や検査で異常がなくても、不快な症状がある場合、それを放置しないで、健康な状態に引き戻そうとするのが東洋医学の考え方です。
自然の素材を活かした漢方素材は、「上薬」「中薬」「下薬」に分類されます。この分類は、漢方素材の良し悪しを区分するものではなく、素材の性質を示すものです。「上薬」「中薬」「下薬」は、その人の症状や体質に応じて使い分けされます。

養命、治療、養生を目的とする漢方。総合的な健康バランスを整える穏やかな作用。副作用がなく、長期的に使用できる。どのような人にも安定的に作用し、健康な人も利用できる。

治療と養生を目的とする漢方。「上薬」と「下薬」の中間的な存在。人によっては有益にも有害にも働く場合がある。

治療を目的とする漢方。作用は比較的強く、長期に渡って使用しないほうが良い。人によっては有害に働く場合がある。

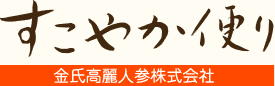
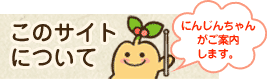

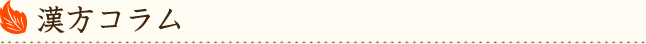
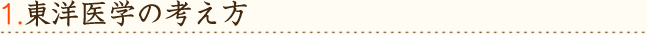
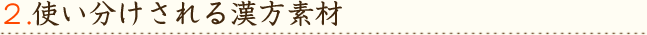
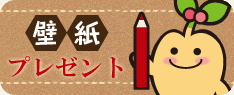

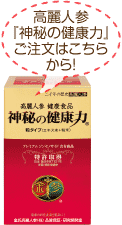
 金氏高麗人参ホームページ
金氏高麗人参ホームページ 運営会社について
運営会社について プライバシーポリシー
プライバシーポリシー